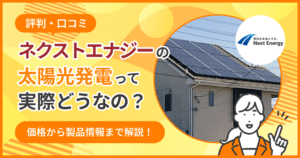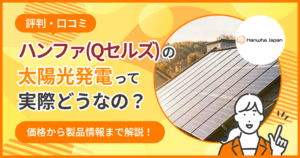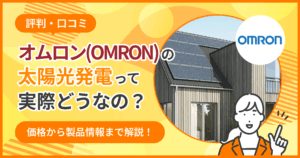「太陽光発電を導入すると確定申告が必要になるの?」
「確定申告が必要な場合、どの税金が課されるの?」
太陽光発電を導入しようと考えているものの、確定申告が必要なのか、どの程度税金が回収されるか不安な方も多いでしょう。太陽光発電で確定申告が必要なケースは限られていますが、必要にも関わらず無申告だと罰則が課される可能性があります。
後々損をしないためには、確定申告が必要なケースを知り、ご自身が当てはまるか慎重に判断することが重要です。
そこで本記事では、太陽光発電を導入して確定申告が必要になるケースや、課される可能性のある税金について解説します。さらに、経費計上の対象となる項目についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
なお、そもそも太陽光発電について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
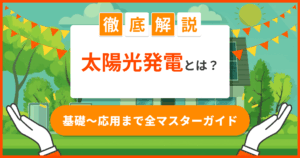
- 売電収入が年間20万円を超える場合には確定申告が必要になる
- 太陽光発電を導入すると消費税・所得税・住民税・固定資産税がかかる可能性がある
- メンテナンス費やローンの利息などは経費として認められる
- 補助金は原則経費計上できないため注意が必要
確定申告とは?

確定申告とは、1年間で得た所得にかかる税金を算出し、20万円を超えた場合に必要となる手続きのことです。確定申告を行うことで、次年度に支払うべき所得税や住民税などが確定します。
普段勤務している会社で年末調整を行っている場合、確定申告は原則不要です。ただし、下記のような場合は、年末調整をしていても別途確定申告が義務となります。
- 副業の収入が年間20万円を超えている場合
- 家賃収入が年間20万円を超えている場合
- 投資で得た収入が年間20万円を超えている場合
太陽光発電を導入したら確定申告が必要?
太陽光発電を住宅用として導入する場合、基本は確定申告をする必要がありません。というのも、住宅用として導入する場合は、確定申告が必要になるほどの売電収入は見込めないからです。
しかし、一定の基準を満たす場合は課税対象となるため、確定申告が必要となります。下記では、確定申告が必要となるケースやどのような税金がかかるのかについて、詳しく紹介していきます。
確定申告が必要なケース
太陽光発電で確定申告が必要となるのは、下記のようなケースです。
- 経費を差し引いた売電収入が年間20万円を超える場合
- 経費を差し引いた売電収入を含めた雑所得が、年間20万円を超える場合
- 経費を差し引いた売電収入を含めた事業所得が、年間38万円を超える場合
- 経費を差し引いた売電収入を含めた不動産所得が、年間20万円以上ある場合
ただし、住宅用の太陽光発電を運用して上記の条件を満たす場合はほとんどありません。そのため、原則該当しないと考えて良いでしょう。
一方で、投資などを行っていて副収入を得ている場合は、所得と売電収入の合計額をしっかり確認しておくなどの注意が必要です。
太陽光発電に関する税金の種類
太陽光発電を導入すると、下記4つの税金が課される可能性があります。
- 所得税
- 消費税
- 固定資産税
- 住民税
売電収入を一定以上得ている場合は所得税が課され、設備の購入や施工費の支払い時には消費税が課されます。そして、所得が一定以上超えると住民税が加算されるのです。
また、固定資産税は、産業用だと判断される太陽光発電を導入した場合に支払い義務が生じます。ただし、これらの税金は対策を行うことで支払い額を減らせる可能性があります。
下記の記事では、より具体的な税金の説明と税金対策の方法などを紹介しています。ご自身が支払わなければならない税金の種類を確認したり、可能な限り減税したりしたい場合はぜひ参考にしてください。

太陽光発電の確定申告に関連する所得区分
確定申告の所得区分は、全部で10種類です。その中で太陽光発電の確定申告に関連がある区分は、下記の3つとなります。
どのような場合にどの所得区分で確定申告を行う必要があるか紹介していくので、よく確認しておきましょう。
雑所得
雑所得とは、他の9種類の区分に当てはまらない所得のことです。個人の住宅に太陽光発電を設置し、余剰電力を売電して収入を得る場合は、基本的に雑所得に該当します。
もし雑所得になるか迷った場合は、次項で紹介する事業所得や不動産所得に当てはまりそうかを確認してみてください。どちらにも当てはまらない場合は、雑所得になると判断しましょう。
なお、雑所得には売電収入以外のものも含まれるため、申告可否を判断するには合算値が20万円に届くか考える必要があります。たとえば、副収入が15万円あり、経費を差し引いた売電収入が6万円ある場合は合わせて21万円となることから確定申告が必要です。
一方で副収入が13万円あり、経費を差し引いた売電収入が6万円の場合は合算しても20万円を超えないため申告は不要です。
事業所得
事業所得とは、農業や製造業、サービス業などの事業を営んだ結果生じた所得のことです。太陽光発電関連で事業所得となるのは、個人事業主や法人が売電所得を得た場合のため、個人の場合は該当しません。
さらに具体的に解説すると、下記のようなケースだと事業所得に該当します。
- 個人事業主や法人として売電収入を得ている場合
- 他の事業に付随して売電収入を得る場合など
他の事業に付随して売電収入を得る場合とは、店舗を併設している個人宅に太陽光発電を導入し、売電している場合などです。これらの所得が合計38万円を超えた場合は、事業所得として申告しましょう。
不動産所得
不動産所得とは、土地や建物を貸した結果生じた所得のことです。太陽光発電関連で不動産所得が発生するのは、貸している土地や建物などに太陽光発電を設置した場合などです。
そのため、基本的に個人宅に太陽光発電を設置する場合は、不動産所得には該当しません。さらに具体的に解説すると、下記のようなケースだと不動産所得に該当します。
- 貸しているマンションの屋上に太陽光発電を設置し、余剰電力で売電収入を得る場合
- 貸している土地に野立ての太陽光発電を設置し、余剰電力で売電収入を得る場合など
貸している建物や土地の売電収入とその他の不動産経営で生じた所得が合計で20万円を超える場合は、確定申告を行いましょう。
雑所得が20万円以上になるか計算する方法
太陽光発電の売電収入を含めた雑所得の合計が20万円を超える場合、確定申告が必要となります。そのため、売電収入を得ている個人の方は雑所得の計算方法を理解し、20万円を超えないか確認しておきましょう。
雑所得の計算は、下記の式で求められます。
年間で売電した発電量÷年間の発電量=売電に充てた発電量の割合
売電に充てた発電量の割合×太陽光発電の購入費×減価償却率(0.059)=必要経費
年間の売電収入-必要経費=雑所得の金額
たとえば、7kWの設備を180万円で購入し、年間で10万円の売電収入を得ていたとします。さらに、売電に充てた発電量の割合が70%であった場合、雑所得の金額は下記の通りです。
必要経費:180万円×0.059×0.7=約7.5万円
雑所得:10万円-7.5万円=2.5万円
この場合、17.6万円以上の他の雑所得があり、売電収入の雑所得と合算して20万円を超えると確定申告が必要となります。
太陽光発電に関して認められる経費の種類
太陽光発電は税金が課される可能性がありますが、下記の項目に関しては経費計上が認められています。
税金対策を行いたい場合、可能な限り経費計上するのがおすすめです。また、経費を計上して一定の金額を下回れば、確定申告自体も不要となります。
ご自身の場合に計上できる項目がどの程度ありそうか、しっかりと確認しておきましょう。
減価償却
減価償却費は、太陽光発電で計上できる経費項目の一つです。減価償却とは、かかった費用を分割して、何年かかけて経費計上することです。
太陽光発電の場合、法定耐用年数の17年に基づいて、定額法という方法で減価償却費を算出します。なお、減価償却費は下記の計算式で求めることが可能です。
設備の取得価額×0.9×経過年数×償却率
固定資産税
太陽光発電を導入すると、場合によっては固定資産税が課されることがあります。この際にかかった固定資産税は、経費計上することが可能です。固定資産税が課されるのは、下記のようなケースです。
- 10kW以上の太陽光パネルを設置している場合
- 事業用として利用している建物に太陽光パネルを設置している場合
- 屋根一体型の太陽光パネルを設置している場合
- 課税標準額が150万円以上の場合
基本的に課税されるのは産業用になるため、一般的な住宅用では固定資産税が課されないことがほとんどと言えます。さらに具体的な内容は下記の記事で紹介しているので、参考にしてみてください。
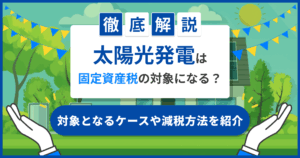
メンテナンス費
太陽光発電に関するメンテナンス費も、経費の一つに含まれます。太陽光発電のメンテナンスは、義務付けられる場合と任意の場合がありますが、どちらも経費の対象です。下記のような場合も経費として認められます。
- 自分自身でメンテナンスを行なった際に必要になった費用
- 設備に不具合が起き、修理や機器の交換が必要となった場合にかかった費用など
ローンの利息
太陽光発電の導入費用は、すでに加入している住宅ローンに組み込んだり、太陽光ローンを組んだりして支払うことが可能です。この際にかかる利息も、経費計上することができます。
ローンを組む方は、年間でかかった利息を計算し、経費に含めるようにしましょう。
諸費用
これまで説明した項目以外でも、下記のようなものが経費の対象となります。
- 土地の賃料
- 太陽光発電の周辺機器代
- 保険料
- パワーコンディショナーの運転費用
- 遠隔システムに関する管理費・通信費
- 太陽光発電について勉強するために購入した書籍代など
上記を見て分かる通り、かなり幅広い太陽光発電の関連費用が経費計上できます。課税対象となり、確定申告が必要な場合は、できるだけ経費で計上できるものがないか確認して申請しましょう。
太陽光発電の確定申告に必要な書類

太陽光発電の確定申告に必要となる書類は、下記の通りです。
- 確定申告書
- 会社員などで年末調整を行う場合は源泉徴収票
- 売電収入額を証明できる通帳などの書類
- 太陽光発電の導入にかかった費用に関する領収証・売買契約書など
- パワーコンディショナの運転費用に関する納付書
土地の売買や賃貸契約を行った場合は、それを証明できる契約書の提出が別途必要となります。また、太陽光発電関連の保険に加入している場合も、関連する契約書や領収証をあらかじめ用意しておきましょう。
太陽光発電の確定申告の方法
太陽光発電の確定申告が必要な場合は、郵送かe-Taxを利用したオンラインでの手続きを行い、税務署へ申告しましょう。初めての確定申告で分からないことがある場合は、市区町村が無料で実施している確定申告相談会などへの参加がおすすめです。
また、確定申告は毎年2月中旬ごろから3月中旬ごろまでの1ヶ月間で行われることが多いと言えます。そのため、毎年2月ごろまでには昨年分の所得の計算や書類集めを済ませておくと安心です。
太陽光発電の確定申告に関する注意点
太陽光発電の確定申告を行う際は、下記の2点に注意しましょう。
上記を理解しておかないと想定より多額の税金の支払いが必要となることがあるため、よく確認しておくことが重要です。
補助金は原則経費計上できない
初期費用を抑えるために補助金を受給するケースがありますが、補助金は原則経費計上することができません。というのも、補助金は国や市区町村から支払われており、自己負担したお金だとは判断されないためです。
補助金を使って太陽光発電を導入した場合は、補助金を差し引いた導入費用のみ経費計上するようにしましょう。
確定申告しないと罰則の対象となる
所得税の課税対象者にも関わらず確定申告を行わなかったり、不要だと自己判断し申告しなかったりすると、罰則の対象となります。罰則の内容は、延滞税や無申告加算税の支払いです。
延滞税は確定申告を行わずに放置し続けた期間に対して課されるため、無申告期間が長いほど罰則の金額が増えます。また、無申告加算税についても比較的利息が高いため注意が必要です。
分からない場合でも自己判断をせず、慎重に確認した上で忘れずに申告しましょう。
確定申告が必要か迷った場合の対処法

太陽光発電の導入で確定申告が必要か迷ったら、税理士へ相談し、判断してもらうのが確実です。税理士なら、確定申告が必要となった場合にそのまま申告代行を依頼することもできます。
また、太陽光発電の導入前に確定申告が必要となるか知りたい場合は、候補の業者へ聞いてみるのがおすすめです。業者へ相談すれば、専門知識をもとに的確なアドバイスをもらえるでしょう。
太陽光発電の設置ならトベシンエナジーにおまかせ!

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | FCR株式会社 |
| 屋号 | トベシンエナジー |
| 本社住所 | 〒145-0064 東京都大田区上池台5丁目38-1 |
| 対応エリア | 東京・千葉・埼玉・神奈川・茨城 |
| 提供サービス | 太陽光、蓄電池、リフォーム |
| 公式サイト | https://tobeshin-energy.com/ |
太陽光発電の導入なら、トベシンエナジーへおまかせください。トベシンエナジーは、関東に16店舗を展開し、太陽光や蓄電池の導入をサポートしています。
補助金採択率が94.2%と業界でも高い水準を誇っており、300万円超えの補助金実績もあります。また、保証期間も20年間と業界トップクラスの内容であり、アフターサービスも充実度が高いことが強みです。
Googleの口コミ評価は★4.7と高く、様々なお客様から厚い信頼を寄せていただいています。関東圏内で太陽光発電や蓄電池の設置をご検討中なら、ぜひトベシンエナジーにおまかせください。
トベシンエナジーの施工実績・口コミ
ここでは、トベシンエナジーで実際に太陽光発電・蓄電池を導入した方の施工事例・口コミをご紹介します。
町田市 K様邸



| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| エリア | 東京都 |
| 築年数 | 10年 |
| 実際の導入費用 | 860,000円 |
| 補助金額 | 2,500,000円 |
| 実際に節約できた金額 | 11,010円 |
| メーカー(太陽光) | 長州産業 |
| メーカー(蓄電池) | 長州産業/SPVマルチ |
 お客様
お客様電気代がすごく高いのは数年前から感じてた。どうやって電気代を下げようか色々調べていると太陽光を設置すると東京都から補助金が降りることを知った。
そんなに出ないだろうと思ったら2/3くらいの補助金が降りることを知って取り付けたいと思った。現状取り付けてから電気代も下がってすごくありがたい。
40代 男性
足立区 O様邸






| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| エリア | 東京都 |
| 築年数 | 5年 |
| 実際の導入費用 | 790,000円 |
| 補助金額 | 2,060,000円 |
| 実際に節約できた金額 | 5,550円 |
| メーカー(太陽光) | カナディアンソーラー |
| メーカー(蓄電池) | カナディアンソーラー |



太陽光蓄電池の補助金がかなり出ると聞き、見積もり取得。
合計金額に対し7割ほどの補助を受けられる事を知り、設置を決意。
今後電気代の高騰も懸念しているので、電気代削減にも期待をしています。
30代 男性
まとめ
太陽光発電を導入し、売電収入額が一定水準を超えていた場合などには、確定申告が必要となります。減価償却費や固定資産税などは経費として計上できるため、可能な限り計上してから申告を行うのがおすすめです。
また、確定申告を怠ると延滞税や無申告加算税などの罰則が課されることがあるため、慎重に判断して申告を進めてください。この記事を参考に、税金対策を行いつつ、適切に確定申告を行いましょう。


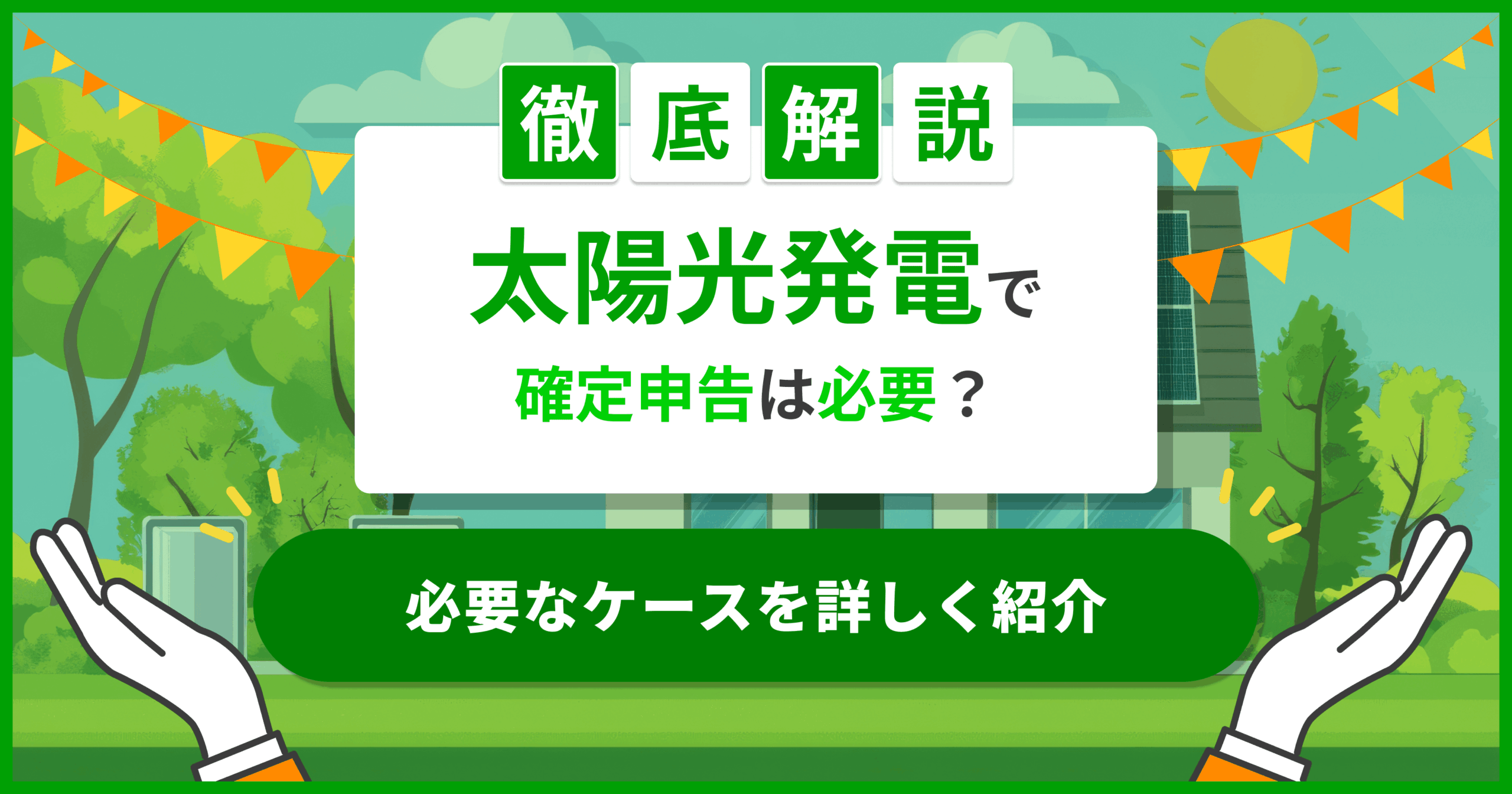

-1-scaled.webp)