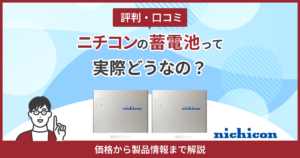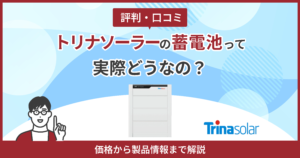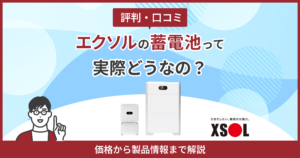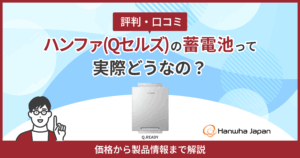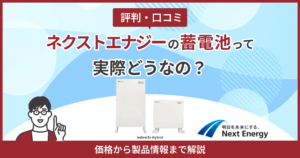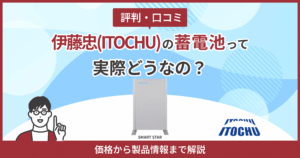「災害時には蓄電池があった方が良いって聞くけど本当?」
「災害時に蓄電池があると、どれくらい電気が使えるの?」
いつ起こるかわからない災害。いざという時、自分や家族を守るために備えておきたいという方も多いでしょう。
災害時に蓄電池があると、停電が発生しても普段通り電気を使って自宅内で過ごすことが可能になります。非常時でも大きな安心感を得られるため、できる限り導入した方が良いといえます。
しかし、実際のところ蓄電池があることで「どの家電が使用できるのか」「蓄電池があることで何時間電気を使えるのか」気になるはず。
そこで本記事では、停電時に蓄電池で過ごせる時間や具体的な使い方を紹介します。さらに、災害時に役立つ蓄電池の選び方も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
なお、そもそも蓄電池とは何かを詳細に知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
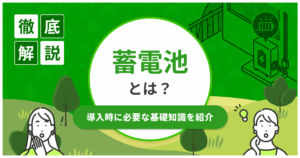
- 災害時に蓄電池があると、停電していてもいつも通り電気を使うことが可能
- 蓄電池のみの場合は停電時に使える電気量がかなり限られるため、太陽光発電との併用がおすすめ
- 災害時に蓄電池を使用するには、自立運転モードに切り替える必要がある
- 災害対策として蓄電池を選ぶ際は、適切な容量・定格出力・電圧・蓄電タイプのものを見極めよう
※なお、本記事ではDR家庭用蓄電池事業やZEH補助事業、環境省などの情報を参考に記事を制作しています。
災害時には蓄電池が必要?
結論、災害時には蓄電池が必要です。なぜなら、今までの日本で起きた災害では、下記のように電気の復旧まで時間がかかっているからです。
| 災害名 | 被害状況 |
|---|---|
| 熊本地震 | ・約47万7千戸が停電(九州電力全社の5.9%に相当) ・地域によっては復旧まで3日程度かかる |
| 台風15号 | ・最⼤約93万4,900⼾の大規模停電 ・倒木の影響などで復旧作業が長期化。おおむねの復旧作業は2日で完了したものの、地域によっては2週間以上の期間を要した。 |
上記の災害時でも蓄電池を導入していて、正常に稼働できている家庭は停電していても復旧を待たずに電気を使えたでしょう。今後も南海トラフ地震や首都直下地震などが懸念されています。
大規模な被害が予想されていることもあり、停電対策は欠かせません。自然災害が多い日本だからこそ、蓄電池を導入して対策しておくことが安全に生活する上で非常に重要なのです。
停電時に家庭用蓄電池で過ごせる時間はどれくらい?
停電時に家庭用蓄電池で過ごせる時間は、下記のケースによって異なります。
それぞれのケースでどの程度の家電を何時間使えるのか、目安を見ていきましょう。
蓄電池のみの場合

停電時に使用できる電気量は、蓄電池の容量によって異なります。今回は、一般的な住宅用として導入されることが多い5kWhの蓄電池の場合を想定し、時間数を算出していきましょう。
今回使用する想定の家電は、災害時でも最低限使用したい下記のものとします。
- 冷蔵庫:60W(100L)
- 照明:30W(リビングでの使用時)
- スマホの充電:10W
- テレビ:100W
- エアコン:600W
- 電子レンジ:1,000W程度
- 洗濯機:300W前後
上記の家電のW数を合計すると、1時間の消費電力は2,100W(=2.1kW)です。つまり、5kWhの蓄電池だと2時間半程度しか持たない計算になります。
なお、上記は容量いっぱいに電気が溜まっていた場合の時間数です。そのため、電気量が減っていた場合はもう少し短くなると考えておきましょう。
太陽光発電と併用する場合

太陽光発電と蓄電池を併用する場合は、基本的に時間数の上限は訪れにくいと考えて良いでしょう。というのも、太陽光発電は太陽光がある限り毎日日中に発電ができ、その電気を随時蓄電池に補充できるからです。
つまり、悪天候が続くなどの状況がない限り、太陽光発電と蓄電池があれば災害時でも問題なく電気を使用し続けられます。ただし、それでも蓄電池の容量の上限はあるため、毎日充電できるからといって電気を使い過ぎないことが大切です。
災害時の蓄電池の使い方
災害時に蓄電池を使う際は、自立運転モードに切り替える必要があります。自立運転モードとは、停電時に蓄電池の電気を使えるようになる機能で、災害時でも残量がなくなるまで電気を使用してくれます。
なお、自立運転モードは災害時に手動で切り替える必要がある場合と、事前の設定で自動で切り替えてくれる場合があります。メーカーや製品によって異なるため、事前によく確認しておきましょう。
また、災害時に初めて運転モードを切り替えるとうまくできない可能性があります。そのため、事前に切り替え方法を確認しておくと安心です。
災害時に蓄電池があるメリット

ここからは、災害時に蓄電池がある場合のメリットをより具体的に解説していきます。
単に電気を使えるだけでなく健康面にも良い影響を及ぼしてくれるため、災害時だからこそ健康に過ごしたい方は必見です。
停電していても電気が使える
蓄電池があれば、災害が起きて停電となった際も家の中で電気を使うことが可能です。スマホを充電したりテレビを見たりすることができ、災害時でも最新情報を集められます。
さらに、大切な人へ連絡を取ることも可能になります。他にも、冷蔵庫や電子レンジなどの家電も使えるため、食料の保存や調理もしやすくなるでしょう。
もちろん照明を使うこともでき、いつも通り安全に過ごすことができます。不安が大きくなる災害時に大きな安心感を得られるのは、最大のメリットだと言えるでしょう。
災害時でも体調管理をしやすくなる
災害時に体調管理をしやすくなるのも、蓄電池のメリットの一つです。蓄電池があれば、夏や冬に災害が起きて停電となってもエアコンを使うことができ、熱中症や風邪などのリスクを避けやすくなります。
災害時は病院を受診すること自体はできるものの、トリアージと言って重症度や緊急度順に診察が行われることになります。軽い風邪などの症状だとすぐに受診できないことがあるため、災害時は蓄電池で体調管理をできるだけ行っておくことが賢明です。
燃料が不要なため安全
発電機の中にはガソリン式のものなどがあり、保管の手間がかかったり駆動音が大きく睡眠に影響が出たりすることがあります。一方蓄電池なら、燃料が不要なため、ほとんど管理の手間なく安全性を確保しながら電気を使うことが可能です。駆動音の心配もありません。
つまり、安全で手軽に管理し、使用時のリスクも抑えたいなら、断然蓄電池が良いと言えます。また、ガソリン式だと災害時に燃料が尽きた場合、調達しない限り使うことができません。
その点、蓄電池なら太陽光発電と併用することで定期的に電気を溜められるため、調達も不要になります。
災害時に蓄電池があるデメリット
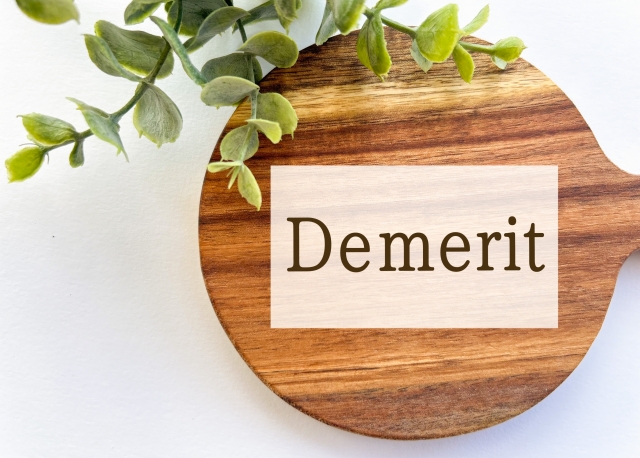
災害時に蓄電池があるデメリットはとくにないものの、下記のようなリスクは考えられます。
- 蓄電池に電気を溜めておらず、停電時に使うことができない
- 災害時の使い方が分からず活用できない
- 火災や水害などで使えなくなったり感電したりする
とはいえ、災害による設備の故障以外は、事前に理解しておくことで十分に対策が可能です。もし火災や水害などで蓄電池が故障した場合は、二次被害が出る前にできるだけ迅速に業者へ相談しましょう。
その際、蓄電池を触ってしまうと感電などのリスクがあるため、絶対に触らないようにしてください。
災害時に活躍する蓄電池のタイプ
蓄電池には2つのタイプがあり、どちらを選ぶかで災害時にできることが変わります。
それぞれどのようなメリット・デメリットがあるか紹介していくので、比較した上で希望のタイプを見つけてみてください。
全負荷型
全負荷型とは、災害時に停電が起きた際にすべての部屋でいつも通り電気を使うことができる蓄電池タイプのことです。下記のようなメリット・デメリットがあります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| いつも通り安心して生活できる エアコンや冷蔵庫なども使用できる | 電気の消費量が多く、蓄電池のみでは長時間電気を賄うことが難しい場合がある 高性能なこともあり、導入費用の相場が高め |
なお、全負荷型の費用相場は5kWhで155〜180万円程度です。電気の使用時間や費用の高さよりも、いつも通りどの部屋でも電気を使えることの方が重要な方には、全負荷型がおすすめです。
特定負荷型
特定負荷型とは、災害時に停電が起きた際に特定の部屋でのみ電気が使える蓄電池タイプのことです。下記のようなメリット・デメリットがあります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 電気消費量を抑えられるため、比較的長時間の使用が可能 全負荷型より安価で購入できる | 全負荷型のようにいつも通り電気を使えるわけではない |
特定負荷型の費用相場は、5kWhで75〜100万円です。全負荷型と比較すると1/2程度で済みます。そのため、特定負荷型は通常通り電気を使用することよりも、長時間の電気使用や導入費用の安さを重視する方におすすめです。
災害時に活躍する蓄電池の選び方
災害時に活躍する蓄電池を選びたい時は、下記の4つのポイントに注目しましょう。
それぞれ具体的な目安や上記のポイントが重要な理由を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
希望に合った容量を選ぶ
蓄電池は製品によって容量が異なり、容量に応じて溜めておける電気や使える電気の量が変わります。つまり、災害時にどの程度の家電を何時間使用したいかによって選ぶ製品が変わるということです。
例えば、下記の必要最低限の家電を24時間使いたいと仮定する場合、5〜19kWh程度の容量の蓄電池が必要になります。
- 冷蔵庫(100L):60W
- スマホの充電:10W
- リビングの電気:30W
- テレビ:100W
- エアコン:600W
なお、エアコンを使わない場合と使う場合で、下記の通り必要な容量が異なります。
エアコンを使わない場合:(冷蔵庫60W+スマホの充電10W+リビングの電気30W+テレビ100W)×24時間÷1,000=約5kWh
エアコンを使う場合:(冷蔵庫60W+スマホの充電10W+リビングの電気30W+テレビ100W+600W)×24時間÷1,000=約19kWh
いつも通りの電気量を災害時にも使用したい場合は、普段の1日あたりの電気消費量と同程度の容量の蓄電池がおすすめです。過去1ヶ月間の電気消費量を検針票などで確認し、日割りで算出してみましょう。
さらに詳しく蓄電池の容量について知りたい方は、下記の記事を参考にしてみてください。
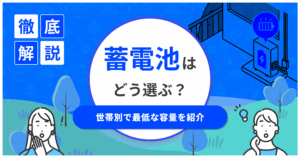
蓄電池のタイプを選ぶ
蓄電池には、全負荷型と特定負荷型の2つのタイプがあります。下記のように用途や希望に合わせて、どのタイプを選ぶか決めておきましょう。
- 全負荷型:災害時に太陽光発電と連携しながらすべての部屋でいつも通り電気を使いたい
- 特定負荷型:災害時に太陽光発電と連携しながら特定の部屋で長時間電気を使いたい
また、蓄電池のタイプによって費用相場も変わるため、価格との兼ね合いを見ながら決めるのもおすすめです。ご自身で希望に合った製品を見つける時間がない場合は、希望条件だけ伝えて業者へ依頼するのも良いでしょう。
定格出力で選ぶ
同時に使いたい家電の種類や数に応じて、適した定格出力を持つ蓄電池を選ぶことも重要です。定格出力とは、一定の時間の間に放電できる量のことで、kW(キロワット)という単位で表されます。
例えば、5kWの定格出力がある製品なら、5kW(=5,000W)分の家電を同時に利用できるのです。5kWあればエアコンや冷蔵庫、テレビ、部屋の照明など必要な家電は同時に使える計算になります。
事前に災害時に同時に利用したい家電の数と総W数を把握しておき、W数に合った定格出力がある製品を見つけてみてください。
高電力の家電を使うなら200V対応を選ぶ
通常の家電のみを使用したいなら100V対応の蓄電池で十分なものの、高電力の家電は200V対応でないと使用できません。高電力の家電とは、IHや200Vのエアコン、エコキュートなどです。
なかでも、エアコンは季節によっては健康状態に大きく影響してしまう家電で、災害時でも積極的に使いたいものでしょう。そのため、災害時により安全で快適に過ごしたいなら、200V対応の蓄電池を選ぶようにするのがおすすめです。
200V対応の蓄電池かどうかは、仕様書や公式HPなどを見たり、業者へ相談したりすると確認できます。
災害時の蓄電池のおすすめ製品一覧
ここまで紹介した蓄電池の選び方を踏まえ、災害時に活用できるおすすめの蓄電池を紹介します。
| メーカー | 製品名 | 蓄電タイプ | 容量 |
|---|---|---|---|
| ニチコン | ESS-U4X1 | 全負荷型(200V対応) | 16.6kWh |
| オムロン | KPBP-A-SET-HYB65-TS | 全負荷型 | 6.5kWh |
| 長州産業 | Smart PV Multi | 特定負荷型・全負荷型両方有 | 6.5kWh~ |
| SHARP | JH-WB1621 | 特定負荷型 | 4.0kWh(定格) |
| オムロン | KPBP-A-SET-HYB65-NS | 特定負荷型 | 6.5kWh |
それぞれ容量や蓄電タイプが異なるため、ご自身に合った製品を参考にしてみてください。なお、他のメーカーでも災害時に役立つ蓄電池は多く販売されています。
そのため、気になるメーカーがあれば蓄電タイプなどを確認の上、上記の表の製品と性能や価格を比較してみましょう。種類が多くどの製品が良いか判断がつかない場合は、業者へ相談するのがおすすめです。
蓄電池導入時に使える補助金一覧
蓄電池を導入する際は、補助金を活用することができます。補助金を活用すれば初期費用を抑えられ元を取りやすくなったり費用対効果を高めやすくなったりするため、積極的に利用しましょう。
また、蓄電池の補助金は国や県、市区町村などで実施されています。国で実施されている補助金は、下記の通りです。
それぞれ要件や補助額がことなるため、詳細を確認した上で希望に合ったものを選んでみてください。さらに、補助金によっては併用ができることがあります。
併用可否を確認した上で、可能な限り組み合わせて申請しましょう。さらに詳しく蓄電池の補助金を知りたい方は、下記の記事を参考にしてみてください。

蓄電池の設置ならトベシンエナジーにおまかせ!

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | FCR株式会社 |
| 屋号 | トベシンエナジー |
| 本社住所 | 〒145-0064 東京都大田区上池台5丁目38-1 |
| 対応エリア | 東京・千葉・埼玉・神奈川・茨城 |
| 提供サービス | 太陽光、蓄電池、リフォーム |
| 公式サイト | https://tobeshin-energy.com/ |
停電対策として蓄電池の導入をお考えなら、トベシンエナジーへおまかせください。トベシンエナジーは、関東に16店舗を展開し、蓄電池の導入をサポートしています。
全負荷型を導入する場合はとくに費用が高くなりますが、トベシンエナジーは自社施工のため初期費用を抑えられます。補助金の代理申請も行っており、採択率は94.2%と高水準です。
できるだけコスパ良く災害対策として蓄電池を導入したい方は、ぜひトベシンエナジーへご相談ください。また、災害対策として適切な蓄電池が分からないというお客様も、一度お気軽にご相談いただくのがおすすめです。
トベシンエナジーではお客様一人ひとりに合ったご提案を行っており、ご希望に沿った製品の紹介が可能になります。ぜひお気軽にご相談ください。
トベシンエナジーの施工実績・口コミ
ここでは、トベシンエナジーで実際に太陽光発電・蓄電池を導入した方の施工事例・口コミをご紹介します。
町田市 K様邸



| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| エリア | 東京都 |
| 築年数 | 10年 |
| 実際の導入費用 | 860,000円 |
| 補助金額 | 2,500,000円 |
| 実際に節約できた金額 | 11,010円 |
| メーカー(太陽光) | 長州産業 |
| メーカー(蓄電池) | 長州産業/SPVマルチ |
 お客様
お客様電気代がすごく高いのは数年前から感じてた。どうやって電気代を下げようか色々調べていると太陽光を設置すると東京都から補助金が降りることを知った。
そんなに出ないだろうと思ったら2/3くらいの補助金が降りることを知って取り付けたいと思った。現状取り付けてから電気代も下がってすごくありがたい。
40代 男性
足立区 O様邸






| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| エリア | 東京都 |
| 築年数 | 5年 |
| 実際の導入費用 | 790,000円 |
| 補助金額 | 2,060,000円 |
| 実際に節約できた金額 | 5,550円 |
| メーカー(太陽光) | カナディアンソーラー |
| メーカー(蓄電池) | カナディアンソーラー |



太陽光蓄電池の補助金がかなり出ると聞き、見積もり取得。
合計金額に対し7割ほどの補助を受けられる事を知り、設置を決意。
今後電気代の高騰も懸念しているので、電気代削減にも期待をしています。
30代 男性
災害時の蓄電池に関するよくある質問


最後に、災害時の蓄電池に関するよくある質問を紹介します。
災害時に蓄電池は太陽光発電と併用した方が良い?
災害時には、蓄電池と太陽光発電の併用がおすすめです。なぜなら、蓄電池だけだとあらかじめ溜めておいた電気しか使用できないからです。
太陽光発電があれば日中に発電し、蓄電池へ充電することができます。つまり、災害時でも継続的に蓄電池の電気を溜めたり使用したりすることができるのです。
実際に千葉市では、自然災害対策で太陽光発電と蓄電池を整備しており、仙台市では防災対応型太陽光発電システムを導入しています。震災が起きてから復旧までには2週間以上かかることもあるため、併用することでより大きな安心感を覚えられるでしょう。
災害時の蓄電池の使い方で注意すべき点は?
災害時の蓄電池の使い方で注意した方が良いのは、下記の2点です。
- 日頃から蓄電池内の電気を一定溜めておいたままにすること
- 災害時にはできるだけ節電し、無駄な電気を使わないよう気を付けること
そもそも蓄電池に電気がない状態だと、せっかく災害対策として導入していても使用することができません。事前に蓄電池の残量設定を行っておき、常に一定の電気残量がある状態を保ちましょう。
また、太陽光発電と蓄電池を併用していたとしても、いつ悪天候となり充電できなくなるか分かりません。そのため、何かあっても慌てずに済むように電気はできるだけ節約しながら使いましょう。
ポータブル蓄電池も効果はあるの?


ポータブル蓄電池とは、小型で持ち運びができる蓄電池のことで、キャンプなどでよく使用されます。ポータブル蓄電池でも災害時の停電対策は可能なものの、家庭に設置されるような定置型蓄電池よりも効果は薄いでしょう。
というのも、ポータブル蓄電池は小型のため、長時間の使用や出力が大きい家電の使用が難しいのです。また、太陽光発電と連携して発電した電気を溜めたり使ったりすることができない製品が多く、自宅内の電気を補うこともできません。
そのため、ポータブル蓄電池ではかなり一時的な停電対策にしかならないと考えておきましょう。
まとめ
本記事では、災害時の蓄電池の必要性や種類、選び方などについて紹介しました。蓄電池があれば災害時でも一定時間は安心して過ごせる上、太陽光発電と併用すればより大きな効果を期待することができます。
ただし、製品によって性能が違い、期待できる停電対策が異なります。そのため、この記事を参考にご自身の希望に近い蓄電池の特徴を見極め、より安心できる性能を持った製品を選んでみてください。


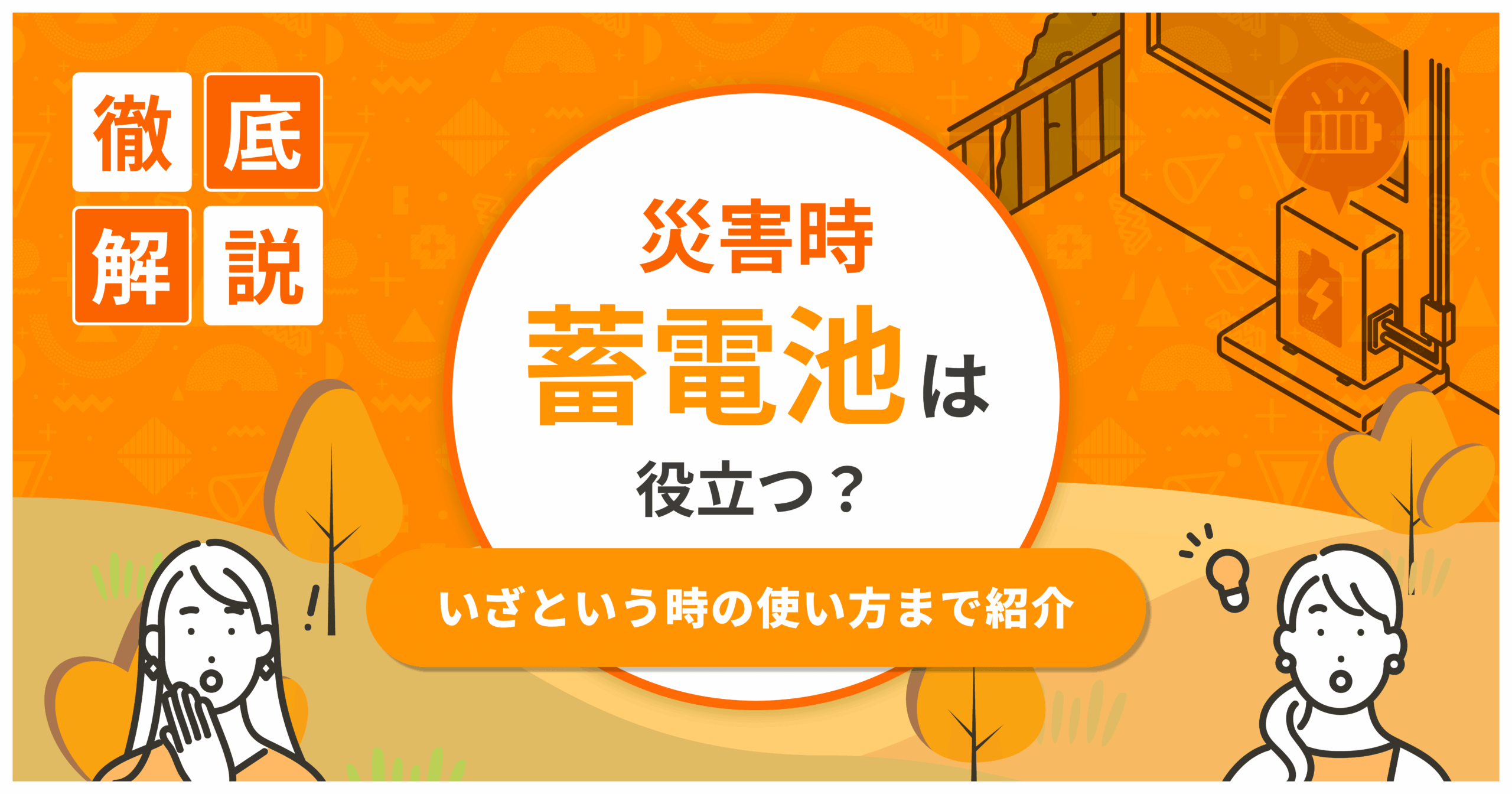

-1-scaled.webp)